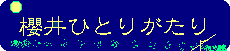「パリスの壺」
(五)
やっと休日を迎えました。菫色のカーテンが、物憂げな日曜の光を透かしています。その端に僅かな隙間を作り、私は外をうかがいました。
灰色の工場と、そこで働く人達の住む建て売り住宅が、四角いパズル・ピースとなって周りを埋めつくしています。煙を吐いている煙突も見えます。この辺りには火を絶やせぬ鋳物工場が多いと聞きました。多分あれがそうでしょう。
物質の豊富さは人を幸福にするはずなのに、どうしてそれを生み出すこの街は、嫌気がさすほど醜いのでしょう。なぜ、朝、工場に向かう人々は、蒼い死人の顔をしているのでしょう。むかし読んだ小説の、そんな言葉が思い出されます。
「あなたは分かる?」カーテンを閉じ、彼の胸に頬を寄せると、自然に答が浮かんできました。
物質は人間の性質を映す鏡です。かってそれは、流れゆく歳月と人々の手に磨かれ、自然の美に溶け込むことができました。けれど今はどうでしょう。
産業が生活を消費に変え、自分達が余剰と廃却の運命に追いやられたその時から、物質は醜さをもって人間に反抗を始めました。でもその醜さとは、けっして物本来が持つ性質ではなく、作り手である人間の卑しい作為、金銭への欲望、名誉を追う虚栄心、流行へのおもねりの反映に他なりません。私達は、消費文明の拡大と引換えに心安まる自然や工芸の美を失い、つねに周囲に充ちる醜さのなかで、心すり減らす毎日を強いられているのです。
それでもまだ、現代に生きる私達に残された美の性質があるとしたら。私がそれを男女の性と答えたら、意外に思われるでしょうか。
私達は「~のために」という打算ゆえ、男や女に生まれついたのではありません。人間のあらゆる作為から離れた自然の摂理、必然の運命、だから性はそのままにして美しい唯一の性質であり、恋はひたすらに尊い感情であることを、私はやっと理解できたのです。
私よりもきれいな人達、異性との付き合いが豊富な人達は、とっくにそれを知っているはず。なのになぜ、世間は性を継子扱いするのでしょう。
もう、これくらいにしておきましょう。要するに私はパリスといるだけで、美しいものへの仲間入りができるのですから。
あれ以来、パリスの胸で眠るのが習慣となりました。彼は、忘れていた幸福の記憶を、夢の形で教えてくれます。ほら、今もまた。
――白い砂丘を越えると、視界いっぱいに海が広がりました。手前、遠浅の浜は金色にひかり、沖は、深い群青をたたえています。海岸線をすべる船は、雲に抱かれて宙に浮かんでいるようです。
「早くう、こっちよ」誰かが波打ち際で手を振りました。日焼けした肌に、ピンクのワンピースがよく似合う・・・・・・ええと、彼女は・・・・・・そうそう思い出しました。
小学校四年の夏休み、私たち一家は一週間海沿いの町に滞在しました。その時お世話になった民宿の子です。学年が同じだったせいもあり、ふたりはすっかり仲良しになりました。
「呼び出してごめんね。今日でお別れだから、これを渡したかったの」
そう言って彼女は、大きな牛乳ビンを差し出しました。中には、色とりどりのキャンディに似た小片が、ぎっしりと詰まっています。正午前の陽射しを透かし、それは二人の影に虹色の橋をかけました。
「わあ、きれい。これなあに」
「波に洗われて角がとれたガラスのかけらよ。砂浜でひろったの」
「これだけ集めるのに大変だったでしょう」
「二年生の頃から少しずつ集めてきたの。その中から、きれいなのばかり選んだのよ」
「そんな大事な宝物を、私がもらっていいの」
「もちろんよ。親友のしるしだもの」
「親友、わたしが?」
「そうよ、めいわく?」
正直言って信じがたかったのです。学校でも、家でも除け者の私にとって、その言葉は八月の太陽がくれた奇跡のように思えました。
「とんでもないわ、大感激よ。こんど会う時は、私が親友のしるしをあげるわ。本当にありがとう」
「約束だよ。来年もきっと会おうね」
それから、あの町を訪れることはありませんでした。彼女、今頃どうしているかしら。きっと結婚して子供もいるでしょう。その子もまた母親を真似て、浜ひるがおの咲く海岸で、虹色のかけらを集めているのでしょうか。
なんだか切なくなって、パリスに身を寄せました。胸も、おなかも、脚も、隙間なくぴったりと。すると、さっき起きたばかりなのに、私はまた睡くなってしまいました。
(六)
「おっはよう」
「きゃっ」
「またしても歩美女史であったか。失礼しました」例のお触り男です。
「またしても私で悪かったね。早く広報課行って口直ししたら」
「そう、怒らなくてもいいでしょう。苦心のお化粧が台なし・・・・・・。ん、歩美女史、いやにきれいだな」
「朝からおかしなこと言わないで。早く有香ちゃんにお触りしないと、仕事が始まっちゃうわよ」
「いや、今日はこの感触を大事にとっておきたい。ちょっとキザだったかな。明日も触るからよろしく」
「ばか」
* * *
「悪いけど、これ十部コピーしてくれないかな」
「今すぐですか」
「ああ、報告書の資料からぬけてたんだ。できたら会議室まで持ってきてほしい」
課長大嫌い。面倒臭いことは、私にばかり頼むんだから。舌打ちをしてコピー機に近付くと、前の人が紙づまりの処理に四苦八苦していました。私の陰口を言っていた女の子です。
黙って待とうと思いましたが、その不慣れな手つきがだんだんともどかしくなりました。思いきって私は、救いの手を差し延べました。
「このレバーを倒して手前に引くの。ほらね、ここに紙があるでしょ」
私を見て彼女の顔色が変りました。弱った魚のようにぱくぱく口を動かしますが、まったく声が聴こえません。「このまま続きをやればいいのね」と訊ねたら、こくりとうなずいたものですから、私が再開のボタンを押しました。
「ありがとうございました」やっと蚊の鳴くような声がして、「先輩、この間は申し訳ありませんでした」と彼女は頭を下げました。
「安心して、気にしてなんかいないわよ」
彼女はなおも頭を垂れたままです。
「もう、いいわ。そんなにされると困っちゃうから」
ぽんと肩に手を置いたら、彼女の身体がすうっとこちらに傾いてきました。反射的に身をかわすと、彼女はそのまま私の足元に倒れました。
「××さん、大丈夫? お願い、誰か来て」
たちまち周りに人垣が出来ました。「医務室へ運べ」「いや、動かさないほうがいい」「救急車を呼べ」、みんなが口々に叫びました。私は彼女を仰向けに起こし、舌を噛んでいない事を確かめました。そして男の人を遠ざけブラウスの胸元を緩めようとした時、彼女は微かにこう呟いたのです。「ごめんね、わたしのあか――」
あとは近づく救急車のサイレンに邪魔され、聞き取ることは出来ませんでした。
* * *
それから三日が過ぎました。まだ彼女は会社に出てきません。
「私のことを気に病んだせいかな」
パリスに相談してみました。もちろん彼の口は閉じたまま、でもこの頃には、私達は心で会話が出来るようになっていたのです(私はそれを、まったく当然のことと受け止めていました)。
「あなたは、私怨を越え人を思い遣る優しい気持の持主だ。だがそのやさしさこそ、実はあなたの欠点の裏返しでもある。あなたのいけないところは、他人より自分自身を愛さないことだ。本当のことを言おう。あなたは自己を嫌悪し苛め抜いたすえ、その傷つきやつれた姿を鏡に映しては、虐げ、虐げられる者の悦び双方に酔いしれている。本当のあなた自身からみれば、他人に接するあなたの態度は偽善者そのものだ」
「なぜ、そんな意地悪を言うの。いつものように優しく私を慰めて」
「慰められるべきはあなたじゃない、あなたにすら愛されない、あなた自身だ」
「もっと我が儘に、自己中心に生きろ、と言うの」
「自己愛とは、自らをより高い存在へといざなうための精神の羽ばたきだ。それを怠る者は永遠に地にとどまり、狡獪な蛇と化して、他者の愛をもとめて這い回る。彼らの愛しているいう告白は、愛されたい、愛されることによって何らかの利益を得たい、という欲望の仮装に過ぎないんだ」
「どうして愛されたいと思ってはいけないの。私達人間にとってあたりまえの感情じゃない」
「それが愛ではなく我欲だからだ。我欲は常に外へ向けられる。外に求める幸福は、決まって誰かの幸福を奪う。奪われた人だって黙ってはいない。今度は彼が、あなたから大事なものを奪う番だ。地上は、こうしたきり無い争いに充ちている。愛という美名のもと、人々は傷つき憔悴する。そして最期は誰もが、傷の痛みと相手への憎しみに身もだえしながら醜い死に様をさらす」
「そんな恐ろしいな話をしてはいやよ。私なら大丈夫。あなたが側にいてくれること以外、何も望まないもの。だいいち我欲を持つすべての人に、絶望的な未来が待っているとは限らないでしょ」
「いや、絶望は我欲の持つ可能性ではなく、我欲の本質だ。外に向かい幸福を求める人は、すでに人生に絶望している」
「もういいわ、あなたの言う通りよ。私、もっと自分を大事にするから、この話はおしまいにして」
「少々きつい言い方だったかもしれない。しかし結果が原因を物語ってからでは遅過ぎる。それを早く、あなたに気付いてほしいんだ」
(七)
闇が、目の前に広がっていました。ろうそくが灯るように、ぽつりと女性の姿が現れました。うずくまり、顔を隠すようにうなだれ、髪は長く、白いパジャマを身につけています。
私は彼女に近づきました。少しかがんで様子をうかがうと、手のひらで小さな塊を抱いているのが見えました。
「きいい」とすねたような声を発し、彼女が頭をもたげました。驚いたことにその顔は、三日前倒れた後輩のものでした。
「××さんじゃない、こんなところで何をしてるの」
どんより濁った視線が私に向けられました。そして震える両手を差しのべながら、彼女はこう言いました。
「ごめんね。わたしのあかちゃんしんじゃった」
手のひらにのる塊の正体は、まだ人の形にもなりきっていない血まみれの胎児でした。
「うっ」と込み上げたものを抑え後ずさると、誰かと腰のあたりでぶつかりました。振り返ると、白髪頭を寝癖でつぶしたお年寄りがいました。
「もう、死なせてください。看護婦さん、早くこの点滴を外してください」
彼女の姿を見た時、私の身体は一個の心臓と化しました。
「おばあちゃん?」
鼻に緑色の管をつけたその顔は、げっそりと肉がそげ落ちていました。けれど私を見つめるその目元に、まだ遠い日の面影が残っていたのです。
「その声は歩美か。待っとたぞ、死ぬ前に一目お前に会いたくて待っとたぞ」
「おばあちゃん、どうしてこんなことに」
私は、その痩せた肩を抱いて泣きました。
「安心して、私がずっと側にいるから」髪を撫で囁きかけると、別人の声が返ってきました。
「あの子は来なかった。親友の約束したのに」
「えっ」とはね退くと、二人の間で何かがガシャンと音をたてて割れました。万華鏡のよう、床に散らばるガラスのかけら。いつの間にかおばあちゃんが、海で出会った女の子になり変わっていたのです。
彼女の話は続きました。
「あの子の乗っていた車と同じだったから、私、思わず手を振って飛び出したの。でも違ってた」
「ごめんなさい。私、次の年も行きたかったけど、お父さんがお仕事忙しくて」
「痛いわ。それにどうしてかしら、ここは寒くて暗いわ。お願い、誰か私をここから連れ出して」
彼女は大きく溜め息をつきました。あの日と同じピンクのワンピースを着ています。その真ん中に走る黒い縞模様は、間違いなく車のタイヤの跡です。
「約束を忘れていないなら、早くここにきてほしい。だって私達、親友だもの」
「許して、私が悪かったわ」耐え切れなくなって、私はその場を逃げ出しました。走り続ける私の両脇に、次々と人の姿が浮かびます。みんな泣いています。みんな何かを訴えています。見たくない聴きたくないと願っても、悲しみに歪む表情や耳をつんざく絶叫が、左右から放たれた矢となって、私の眼や耳を貫きます。
息が切れ、足がふらつきました。ここが地獄と呼ばれる処なのか、そんな疑問がふと頭をかすめました。私は慄然として立ち止まりました。いつの間にか人々の姿は消え、夜の砂漠に似た寂寥が私を包んでいます。だとしたら、私は死んでしまったのかしら? いやよ、そんなのいや。助けて、パリス!
その叫びが彼に届いたのでしょうか、正面に大きな明かりが迫ってきました。柔らかい光の中に浮かぶのは、住み慣れた自分の部屋でした。
本当に嬉しかった。迷わずその中に飛び込みました。真っ先にお礼が言いたくてパリスのもとに駆け寄ると、ベッドの傍らで誰かが泣き伏しているではありませんか。「パリスは?」と、ベッドの上を確かめた時、私はすべてを諒解しました。みずから出した答に承認の印を捺すかのごとく、私はその人の肩に手を置きました。すると泣き腫らした顔が振り向き、私に訴えかけました。
「あの人が、あの人がいなくなっちゃったの」
そこで私は目を覚ましました。暗闇のなか慌てて布団の中をまさぐると、温かい彼の肌に触れました。
「よかった」私は、彼に抱きつきました。
「あなたは何処にも行かない。ずっと私と一緒にいるのよ」
まるで狂女のように、私は彼の身体に口づけました。今視た夢の恐怖を打ち消すために。この人のいないベッドにすがる、自分の姿を忘れるために。
(八)へ続く
|